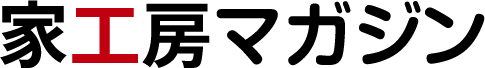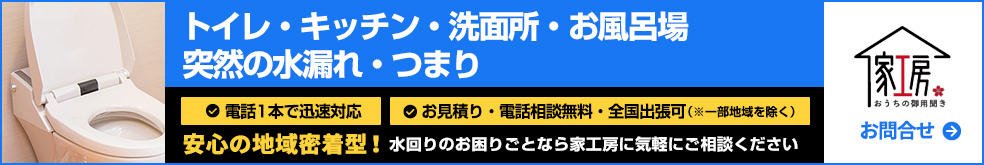床が十分に乾燥できていないとトラブルが生じることもある

水漏れが起こって床が濡れてしまったとき、「水漏れに気づいてすぐに拭き取ったから問題ないのではないか」と思う方もいるかもしれません。
しかし、床をしっかり拭いたつもりでも、乾燥しきれていないことは十分にあります。これは床表面は拭き取れていても、床の隙間から水が浸水して水分が残ってしまうこともあるためです。
そのまま放置して十分に乾燥されないと、さまざまなトラブルの原因になります。黒いシミとなったり、水分を好むカビが発生して、黒カビが床を覆ったりする可能性も考えられます。壁にまで水が浸透してしまっている場合は、壁紙にカビが発生することもあります。
また、木材は一定以上の水分を含むと腐食が始まります。床が腐って柔らかくなったり、床板が浮いてきたりなど、床の傷みが進行する恐れもあります。
このように床になんらかのトラブルが生じた場合は、床の変色などを抑える補修作業が必要になったり、床の腐食が進行した場合は、根本的に修繕するために床を張り替えなければならなくなったりします。
大掛かりな工事が必要になるほど、修繕にかかる時間もコストも必要になります。床への水漏れに気付いたらしっかり内部まで乾くよう早急に対処することが大切です。
水に濡れた床を早急に乾かす方法

早速濡れた床を乾かす手順を紹介します。
漏水時の床掃除で乾燥が非常に重要であることはご理解いただけたと思うので、ここからは床の乾かし方を解説します。
1.まずは床のおおまかな水気をとる
まず、濡れている部分の水をおおまかに拭きとります。水漏れの程度にもよりますが、基本的には雑巾などに床の水を含ませ、バケツに絞る作業を繰り返します。
なかには雑巾での拭き取りだけでは処理しきれない場合もあります。水漏れが広範囲であったり、水の量が多かったりした際は、モップなどを使ってできるだけ早く水分を除去するのが望ましいです。
雑巾やモップである程度の水分を取り除いたら、次に乾拭きをしていきます。効率良く乾拭きするには、新聞紙など吸水性のあるものを使用するのが良いです。しっかりと水分を吸収させ水気を取り除いていきます。
2.扇風機などで乾かす
新聞などで乾拭きまですると床の水分は完全になくなったように感じるかもしれません。しかし、床表面水分は取り除かれたとしても、床の内部に浸透してしまった水分はどうしても残ってしまいます。
乾拭きで安心せず、床の内部までしっかり乾かすことが重要です。早急に乾かすなら、換気だけでなく扇風機など床に風を送りこむような道具を使って乾かしていきましょう。湿度を調整する除湿器も効果的です。
ドライヤーや温風乾燥を使う方法もありますが、熱風は木材を傷めたり変形させたりする恐れもありますので、使用する際は注意しましょう。
なお、扇風機などを使って乾燥を促進させても、内部にどれくらいの水分が残っているかは確かめようがありません。しっかり乾燥させるために、自然乾燥も並行して取り入れましょう。1〜2週間程度換気をすることで、より確実に床内部まで乾燥させることができます。
3.しっかり消毒する
床に浸水した水にはカビのもととなる真菌をはじめ、さまざまな菌が含まれている可能性があります。水には含まれていなくても床に付着していることも考えられます。
カビの発生を防止するために、床を乾燥させたあとは消毒用エタノールなどを使用して消毒をします。
床によっては消毒用エタノールを使用することで変色してしまうことがありますのでご注意ください。よくあるのが、ワックスが施されたフローリングに消毒用エタノールやアルコールを塗布して白くなってしまうケースです。
ワックスで表面加工をしたフローリングに消毒用エタノールを使用すると、ワックスが溶け、ワックスの油分とエタノールの成分が混ざることで気泡が作られます。通常時はほぼ平面だったため光をキレイに反射していましたが、気泡によって凹凸が生まれることで光が乱反射され白く変色したように見えます。このように床材によっては消毒用エタノールやアルコールが適さない場合もあります。
消毒用エタノール以外で床を消毒する方法として、薄めに希釈した次亜塩素酸ナトリウムや食器用洗剤を使用する方法もあります。食器用洗剤はアルコールなどとは違い揮発しないため、使用した後は洗浄成分を取り除くために再度水拭きと乾拭きをする必要があります。
床下まで水漏れしている場合の対応

一軒家など床下がある住宅では、水漏れの被害が床上にとどまらない可能性もあります。
床下まで浸水した場合、湿気によってカビやダニが発生しやすくなるほか、異臭やシロアリのトラブルにまで発展することもありますので、床下浸水に気づいたら乾燥させる必要があります。
床下を乾燥させる方法としては、石灰や温風乾燥機を使用する方法があります。
石灰は、水を吸収する性質をもったものです。床下に石灰をまくことで乾燥を促進させることができます。石灰には、生石灰と消石灰がありますが、生石灰は水で発熱することがあるため、粉末状の消石灰の使用が適しています。
浸水が起きた床下に石灰を数ミリ薄く重ねるように散布していきます。石灰の粉じんは目に入ると危険ですので、ゴーグルなどを使用して散布するようにしましょう。
石灰のほかに、温風乾燥機を使用して乾燥させることができます。温風乾燥は早く乾かすのに適していますが、先述したように熱い風をあて続けると木材を傷めてしまう可能性があります。気になる場合は扇風機などの冷風を送る道具を使用するのが良いです。
水漏れした床を業者に乾かしてもらう方法もひとつ
水漏れの範囲が広いときや長時間放置したことによる被害が心配なときは、業者に床の乾燥を依頼する方法もあります。業者であれば専用の道具などで一気に乾燥させることもできますので、自分で対処するよりはトラブルを回避しやすくなるでしょう。
特に一軒家などで床下浸水が起きてしまった際は、床下の乾燥作業が必要になるため、業者に依頼した方が安心できる面も多い可能性があります。
また、乾燥が行き届かなかったり、拭き取りに時間がかかるなどして長時間床が水にさらされた状態になったりしたときは、後日トラブルが発生することもあります。
冒頭で述べたように、黒いシミやカビが発生したら補修が必要になることもあるほか、床が浮いてきたら床板を直す作業が必要になることもあります。補修で被害状況が改善しない場合は、床材の上から新しい床材を重ねたり、床材自体を張り替えたりする作業が必要になる場合もあります。
床の修繕や張り替えは自分でやろうとするとかえって状況を悪化させる可能性も考えられます。水漏れによる変色や黒ずみ、張り替えなども業者に対応してもらえますので、後にトラブルが生じた際も業者を利用することをおすすめします。
おうちの御用聞き家工房は、おうちに関する些細なお困りごとからリフォームまで、ご自宅の悩みに対応しています。水漏れによる床の乾燥やトラブルにお困りの際はご相談ください。
まとめ
水漏れが起きて床が濡れてしまったときは、しっかり乾かさないとさまざまな床トラブルが発生する可能性があります。水漏れが広範囲に及ぶなど自分で乾燥させるのが難しい場合は、業者に依頼するのも方法のひとつです。