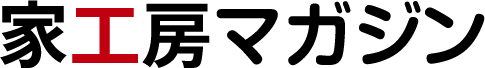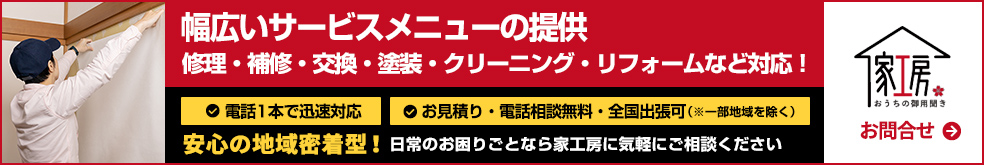雨樋をつまらせる3つの原因

雨樋のつまりには大きく3つの原因が考えられます。どんな原因がつまりを生じさせるのか、具体的にみていきましょう。
土や砂が溜まっている
風などによって土や砂が舞い上がり、雨樋に溜まってつまりの原因となることがあります。
本来、土や砂は雨水と一緒に流れていくものですが、しばらく雨が降らなかったりして多量の土や砂が雨樋に溜まってしまうと、少々の雨水では流れなくなります。その結果、つまりが生じてしまうのです。
特に雨樋は高い場所に位置しているため、普段はなかなかつまりの状態を見られません。気づかないうちに土や砂が溜まり、排水を妨げてしまうことがあるでしょう。
加えて、土や砂が雨樋に溜まってしまうと、その重みによってゆがみや破損が発生してしまう可能性もあります。
落ち葉や花が溜まっている
庭で木や花を栽培しているお宅だと、雨樋に落ち葉や花弁が溜まってしまう可能性があり、それがつまりの原因になることがあります。自宅に木や花を植えていなくても、近所に公園や神社があると、そこで栽培されている木の葉や花が雨樋に落ち、それがつまってしまうこともあるかもしれません。
特に秋から冬にかけては、雨樋に落ち葉が積もってしまっている可能性があります。落ち葉によるつまりを防ぐには、定期的に雨樋をチェックすることが必要です。
鳥の巣ができている
鳥が巣作りのために運んできた藁などの巣材が雨樋に落ちてしまい、それがつまりの原因となっていることもあります。また、雨樋自体に鳥が巣を作っている場合もあるでしょう。
藁などであればすぐに除去してしまえばつまりは解消されますが、鳥が雨樋に巣を作っている場合、すぐに撤去するのは困難です。卵やひながいる巣を勝手に取り除いたり移動させたりすると、鳥獣保護法違反になってしまいます。
そのほかにも、巣材にはボールやペットボトル、空き缶、袋など思わぬものが使われており、それが雨樋の排水を妨げていることもあります。
雨樋のつまりやすい場所をチェックしよう

雨樋のつまりやすい場所は、主に「集水器」と「軒樋(のきどい)」の2つです。それぞれチェックしておきましょう。
集水器をチェック
「集水器」とは、屋根に水平に設置されている軒樋と、軒樋から下方向に伸びている竪樋(たてどい)を繋いでいる部分です。軒樋を伝ってきた雨水は、集水器から竪樋を通って排出されるようになっています。
しかし、集水器には段差やカーブがあるため、この部分に落ち葉や袋などが入るとスムーズに排出されず、つまりが生じやすいのです。
外からは集水器につまりが生じているか確認しにくいことから、雨水があふれているのを見てつまりに気づくケースがほとんどでしょう。
軒樋(のきどい)をチェック
「軒樋」は屋根の軒先に沿って水平に設置された建材です。屋根に降った雨水を最初に集める場所で、そこから雨水は集水器、竪樋を通って排水口へと排水されます。
軒樋は、屋根から流れてきた雨を効率良く受け止められるように上の部分が開いていますが、その形状ゆえに落ち葉や花びら、土、砂などが溜まりやすくなっています。
高い位置にあるため普段は目にすることがなく、気が付いたらたくさんのゴミが軒樋に溜まっていたというケースも珍しくありません。
雨樋のつまりを防止する方法

雨樋のつまりは、そのままにしておくと雨漏りによってシロアリの発生などにつながることがあります。また、台風や豪雨などが起こった際にはオーバーフローの原因にもなるため、あらかじめ対策を講じておくことが大切です。
ここでは、どのように雨樋のつまりを防止するのか、効果的な方法をご紹介します。
定期的に掃除を行う
雨樋はつまりやすいものと心得て、雨樋に落ち葉や土、ゴミなどが溜まっていないかを定期的にチェックし、掃除するようにしましょう。毎月行う必要はありませんが、シーズン毎、半年に1回などと頻度を決めて、年に数回は雨樋掃除をするのがおすすめです。
掃除をする際は、脚立やゴム手袋、ほうき、ちりとり、針金、ホース、ゴミ袋を準備します。鳥の羽やフンなどに触れると、アレルギーなどのリスクがあるため、必ずゴム手袋をつけて掃除しましょう。
軒樋はほうきや手を使って掃除していきますが、集水器や竪樋の部分には手を入れられないため、針金などを使ってゴミを掻き出します。
できる範囲でゴミを取り除いたら、ホースを使って水を流して、スムーズに流れるかもチェックしましょう。
スムーズに水が流れない場合は集水器や竪樋部分のつまりがあるということなので、再度針金などを使って掃除をします。また、水を流しながら竪樋を軽く叩くと、竪樋につまっているゴミが下に落ちやすくなり、つまりが解消しやすくなるでしょう。
平屋の場合は脚立を使っての掃除がやりやすいものの、2階建ての家に雨樋が付いている場合は、高い場所での作業となるため注意が必要です。不安な場合は専門の業者に依頼し、掃除してもらいましょう。
どうしても自分で作業を行いたい場合は、安全対策をしっかりと施し、無理のない範囲で作業してください。
落ち葉除けネットを設置する
定期的に雨樋の掃除をするのが面倒な方は、つまりを防止するために落ち葉除けネット(雨樋カバー)を設置するのがおすすめです。
筒状にしたネットを雨樋に設置すると、雨樋に大きな落ち葉が侵入するのを防げるので、落ち葉のつまり防止になります。また、落ち葉だけでなく、ボール、袋などのゴミがつまるのを防げるほか、鳥が巣を作ることも防げるのがメリットです。
ただし、あくまでも網状のネットなので、土や砂などの小さなものは通してしまう点は覚えておきましょう。また、ネットに枝葉やゴミなどが引っかかることはあるため、数年に1度は掃除してゴミや土砂を取り除く必要があります。
落ち葉除けネットのほかにも、落ち葉除けシートやマルチカバーなどのアイテムを取り付けるのも効果的です。ただし、いずれにしても完全につまりを阻止できるわけではなく、数年に1度は掃除をすることが求められます。
雨樋を新しいものに交換する
何度も雨樋の掃除やつまり対策を講じているのにつまりが生じる場合は、新しく雨樋を交換することを検討しましょう。
もしかすると、以下のような要因が雨樋のつまりにつながっているのかもしれません。
・そもそも屋根からの雨樋の距離が適切でない
・雨樋に歪みが生じている
・雨樋を繋ぐ地中に埋設された配管がつまっている
このようなケースでは、雨樋を新しいものに交換するのを推奨します。雨樋を交換すれば、掃除の頻度が少なくてもつまりが起こりにくくなるかもしれません。
雨樋の交換なら、ご家庭のお困りごとを解決する「おうちの御用聞き家工房」にお任せください。もちろん、「雨樋がつまりやすいので、何が問題か確認してほしい」といったご相談でも大丈夫です。
ご要望をお聞きしたうえで最適な対応をさせていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。
まとめ
雨樋のつまりを防止するには、不具合が生じてからチェックするのではなく、定期的なメンテナンスを行うことが大切です。
土や砂、落ち葉、花、鳥の巣、その他のゴミなどが集水器や軒樋に溜まってしまい、つまりを起こしてしまうのは珍しいことではありません。このようなトラブルを防ぐには、本記事でご紹介したような対策や、場合によっては雨樋の交換も検討してみましょう。